こんにちは。中小企業診断士のなかりょです。
令和6年度の二次試験で、事例Ⅰ67点、事例Ⅱ70点、事例Ⅲ78点、事例Ⅳ77点の合計292点で合格しました。
勉強されている人の中には、
「答案は予備校が出しているような完成度じゃないといけないのでは」と感じる方も多いと思います。
でも実際には、本番80分間で対応できる範囲で情報を整理して書く答案でも十分合格点を狙えます。
令和6年度事例Ⅰ・Ⅱの記事に続き、本記事では事例Ⅲの私の答案をもとに、設問ごとの解答意図や攻略ポイントを解説します。
この記事が少しでも皆さんの参考になればうれしいです。
令和6年度事例Ⅲの答案例と考え方のポイント

事例Ⅲ 設問1(強み分析)の解答例
設問:
C 社の強みを80字以内で述べよ。
答案:
①C社社長に基づく搬送機能についての提案力、②設計、製造要員に基づく設計から製造までの一貫生産体制、③X社メンテナンス担当による顧客ニーズ把握が可能。
解答意図・攻略ポイント:
①後の設問で活用する可能性のある情報を優先する
与件文からSWOTを抽出する際は、後の設問で活用する可能性のある情報を優先する。記述は最後に回し、候補だけメモしておく。
事例Ⅲ 設問2(工程改善)の解答例
設問:
コロナ禍以降増加傾向にある受注量に対応するため、C社製造部では工程改善によって生産能力の向上を図る検討を進めている。
どのように工程改善を進めるべきか、100字以内で助言せよ。
答案:
製缶課の残業、休日出勤の更なる増加が見込まれるため、ジョブローテーションによる多能工化、前後の工程を含めた人員配置の見直しを図る。
作業の標準化とマニュアル化、OJTにより製缶工程の改善を図る。
解答意図・攻略ポイント:
①事業環境の変化に対応するの問題点を抽出する
先ずどの工程に問題があるかを考える。
与件文にある「コロナ禍以降の受注増」という変化を踏まえると、休日出勤が常態化している製缶課はいずれ立ち行かなくなる。
②工程改善の優先順位は(1)オペレーション変更、(2)増員補強
増員補強出来れば改善は進みますが、零細な中小企業が現実的に対応出来る方法(オペレーション変更で改善可能な方法)を優先して助言することが求められる。
工程の人員不足に対してオペレーションの変更で改善できる方法を考える。
特に、「前後工程では残業が発生していない」との文言があるので人員の配置変更により対応可能であると判断する。
事例Ⅲ 設問3(工程管理業務の改善)の解答例
設問:
C社では、受注量の増加や納期短縮要請などの影響で製造部の工程管理が混乱している。
どのように工程管理業務を改善するべきか、その進め方を100字以内で助言せよ。
答案:
IT利用により生産計画、生産統制情報、製作仕様書、図面を一元管理し、リアルタイム共有を図る。
設計、納期変更の際も都度確認、生産順の変更を可能とする。
週次日程計画表作成時の工数見積もりの標準化も進める。
解答意図・攻略ポイント:
①IT利用のフレームワーク「DRINK」を使う
工程管理にIT利用も図りながら対応を検討…との記載があるので、IT利用のフレームワークをそのまま活用する。
D:データベース化
R:リアルタイム
I:一元管理
N:ネットワーク
K:共有化
事例Ⅲ 設問4(価格交渉の事前対策)の解答例
設問:
C社の顧客企業との契約金額は、最近の材料費や人件費の高騰に対応した見直しは行われているものの、現状のコスト高には対応できていない。
今後、顧客企業と価格交渉を円滑に行うための社内の事前対策を120字以内で助言せよ。
答案:
契約金額を材料費と社内加工費とその他経費を分けて管理することで過去参考時の合算算出を防止し、契約前に設計部に製品仕様書等を渡して部品構成表を作成、材料毎の金額をデータに掲載して見積もり精度の向上を図る。
解答意図・攻略ポイント:
①あるべき姿を考える
顧客企業と価格交渉を円滑に行うための要件(あるべき姿)としては、「何にどれだけ」コストが掛かっているかを把握している状態。
交渉の材料として使えるようにしておく必要がある。
②現状を整理する
「見積金額は、過去に製造した搬送機器の契約金額を参考に、営業部員が材料費と社内加工費、その他の経費を合計して算出している」とのことで、最新の材料費や人件費が見積に反映されていません。
また、精緻な見積を行うには部品の構成を明確にしておく必要がありますが、設計部が見積プロセスに関与していないため、「何にどれだけ」という部分がアバウトになっています。
③課題と具体策を考える(あるべき姿と現状のギャップ)
あるべき姿と現状のギャップを埋めるための方策を考える。
コストを日常的に管理していくこと、設計部を見積もりプロセスへ参画させることを解決策として記載する。
事例Ⅲ 設問5(新しい事業展開)の解答例
設問:
C社社長は、小規模の工場施設や物流施設の新設や更新を計画している企業と直接契約し、自社企画の製品を設計、製造することで事業を拡大したいと考えている。
この新しい事業展開を成功させるにはどのように推進するべきか、120字以内で助言せよ。
答案:
営業部を強化し、X社のメンテナンスを通してニーズを把握、自社製品開発へ活用する。
搬送機能の有効な提案力、特注対応力を活用して差別化を図ることで新規顧客の開拓を図る。
解答意図・攻略ポイント:
①強みを活かした施策を検討する
毎年事例Ⅲの最終問題として出ているタイプの問題です。
C社の強みを活かして差別化を図る戦略が求められます。
設問1で検討した強みをベースに戦略を立案する。
事例Ⅲの全体攻略のポイント
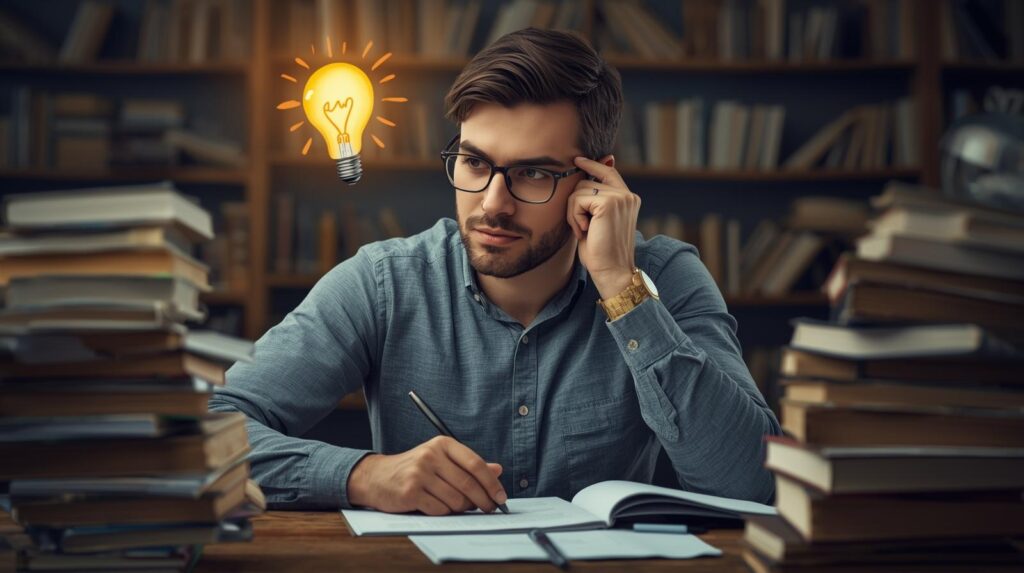
数年前までは、問題のある工程そのものにネックポイント(作業遅延・段取り不良・属人化など)が存在するケースが多く見られました。
しかし近年は、問題工程の前後工程の影響によって問題が発生している ケースが増えています。
例えば、前工程で製品を一定ルールで区画分けして保管していた結果、次工程での運び出しに時間がかかってしまうなど、表面的な問題と真の原因が異なる構造になっています。
令和6年度の事例Ⅲでも、似たような傾向が見られました。
製缶課では休日出勤が常態化していた一方、前後の工程には人員の余裕があり、工程間の人員配置バランスの不均衡が根本原因であったと考えられます。
このように、「問題が発生している工程だけに注目する」のではなく、前後の工程の関係性を含めて全体を俯瞰する視点が求められています。
まとめ

事例Ⅲでは、「問題のある工程」だけに注目するのではなく、工程全体のつながりの中で原因を考えることが重要です。
前後の工程を含めて問題の構造を捉えることで、根本原因にアプローチした説得力のある答案が書けるようになります。
ぜひ、“工程を俯瞰する視点”を意識して取り組んでみてください。
この記事が少しでも読者の皆さんの得点力向上につながれば嬉しいです。
事例Ⅰ(人事・組織)と事例Ⅱ(マーケティング)の記事はこちら👇
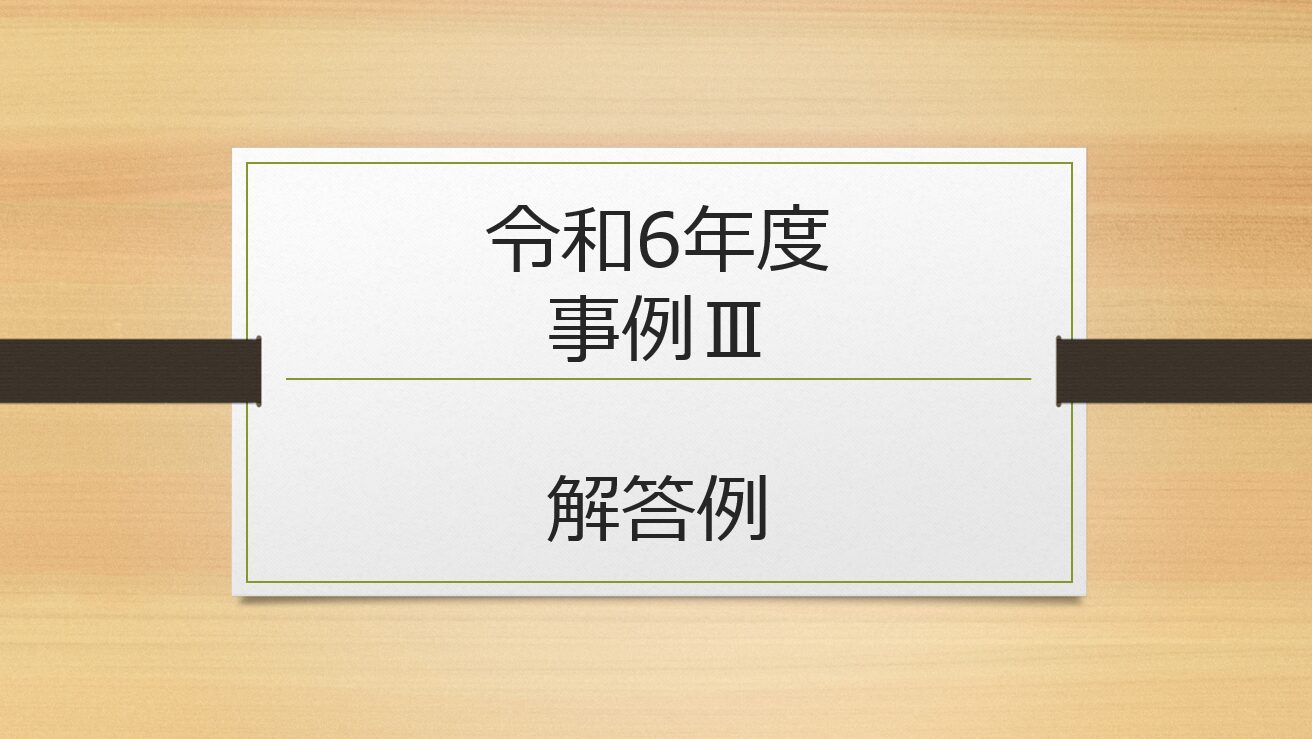




コメント