こんにちは。
中小企業診断士のなかりょです。
資格取得を目指して勉強を始めようと考えたとき、
「とりあえずテキストを買って読み始めよう」
「科目もとりあえずひとつずつ進めていこう」
と考える方は意外と多いと思います。
わたしも簿記や宅建など色々な資格の勉強をしてきましたが、中小企業診断士は他の資格試験と比べてかなり特殊です。
試験範囲は一次と二次を合わせて非常に広く、科目の性質も暗記・理解・思考型とバラバラ。
しかも、合格までの勉強時間は約1000時間と言われているので、闇雲に勉強を始めると、この膨大な時間をロスする可能性があります。
この記事では、診断士試験に挑戦するすべての方を対象に、勉強初期に欠かせない「どんな情報を知っておくべきか」を整理しています。
この記事が少しでもお役に立てると嬉しいです。
勉強初期に押さえるべきポイント

情報収集の目的は「最短で確実に合格にたどり着くこと」
最短で合格に近づくために、勉強初期に整理しておくべきことは主に3つです。
これらを理解することで、単なる暗記や問題集演習に走る前に、合格への設計図を描くことができます。
何を知っておくべきか — 勉強初期に押さえる情報
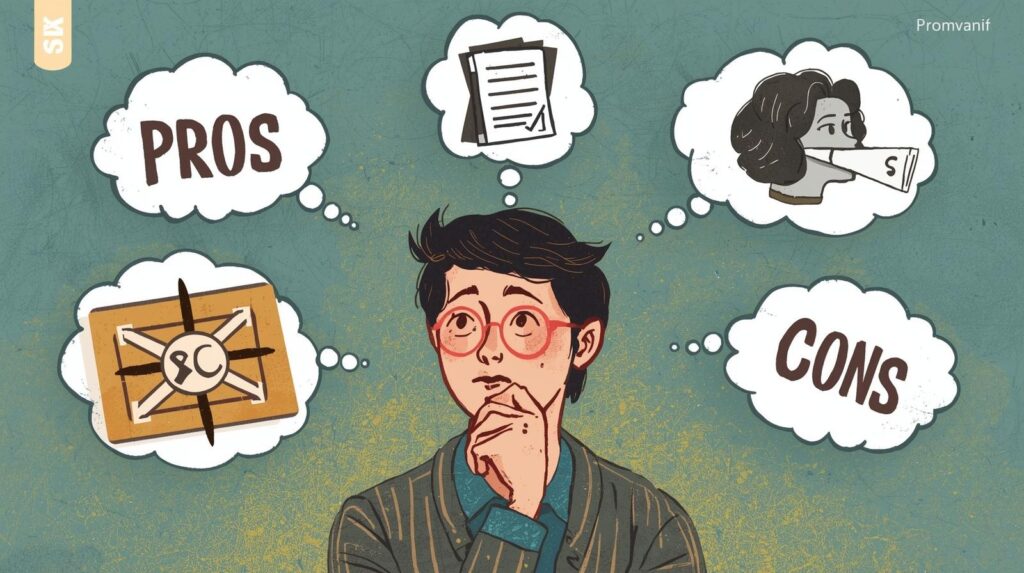
中小企業診断士の試験全体の構造
診断士試験は、一次試験 → 二次試験(筆記) → 二次試験(口述試験) の3段階で構成されています。
| ステージ | 内容 | 合格基準 | 学習の焦点 |
|---|---|---|---|
| 一次試験 | 7科目のマークシート式 | 各科目40点以上+総合60%以上 | 幅広い知識のインプットと基礎理解 |
| 二次試験 | 4事例の記述式 | 各事例40点以上+総合60%以上 | 一次知識を応用して事例企業を診断・助言できる力 |
| 口述試験 | 面接形式 | 出席かつ最低限の理解でほぼ合格 | 二次理解度の確認 |
一次試験には「科目合格制度」があります。
これは、一次試験で60点以上を取った科目は翌年度以降に免除できる制度です。
たとえば、7科目のうち3科目で60点以上を取れば、翌年は残り4科目だけを受験できます。
また、また、一次試験にすべて合格すると、その年と翌年の2回、二次試験を受験する資格が得られます。
この仕組みを理解しておくと、「一年で一発合格を狙う」か「二年計画で確実に突破する」かという自分に合った受験戦略を立てやすくなります。
科目ごとの特性と学習のポイント(一次試験→二次試験)
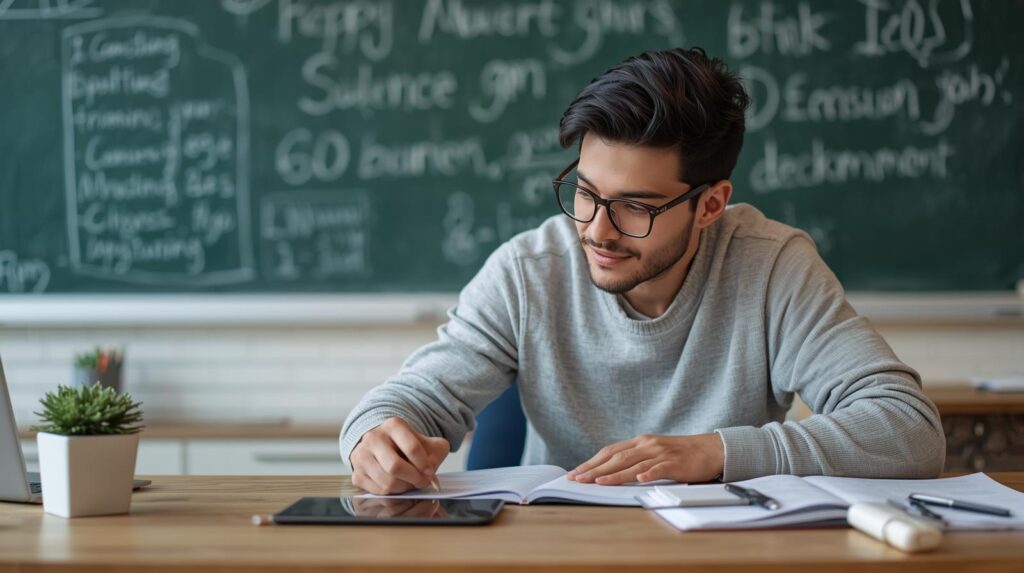
| 科目 | 主な内容 | 学習ポイント | 難易度 (体感) |
|---|---|---|---|
| 経済学・経済政策 | マクロ・ミクロ経済 経済理論 | グラフと数式の理解が中心 | ★★★★☆ |
| 財務・会計 | 簿記・会計・ファイナンス | 数値処理が多いが、理解すれば得点源に。反復練習がカギ | ★★★★★ |
| 企業経営理論 | 経営戦略・組織論・マーケティング | 理論の暗記に偏りすぎず、具体例とセットで理解必要 | ★★★☆☆ |
| 運営管理 | 生産管理・店舗販売管理 | 現場知識が多く、イメージしやすい | ★★☆☆☆ |
| 経営法務 | 会社法・知的財産法・民法 | 用語と条文が多く、初学者には取り付きにくい。繰り返し暗記 | ★★★★☆ |
| 経営情報システム | IT基礎・システム管理 | ITに苦手意識があると難しく感じる。繰り返し暗記 | ★★★☆☆ |
| 中小企業経営・政策 | 中小企業白書・政策制度 | 暗記量が多く、直前期に集中的に対策するのが効果的 | ★☆☆☆☆ |
一次試験の知識は二次試験での材料になります。
科目と二次試験の事例の関係性は下記の通りです。
一次試験の科目知識・理解を応用して、二次試験の事例企業を診断・助言していくことになります。
しかし、全ての科目が二次試験に繋がるわけではありません。
合格者に共通する勉強パターン

多くの合格者に共通するのは、自分だけのやり方に頼らず、合格者の勉強法を研究していることです。
研究した内容を自分の勉強スタイルに取り入れて、効率的な学習に結びつけています。
合格者の学習法を調べる
下記は一例ですが、色々な切り口で勉強方法について調べてみることをおすすめします。
私はYoutubeで調べることが多かったですが、個人ブログ、Xなどでも情報収集していました。
| 切り口 | 具体例 |
|---|---|
| 一次/二次別の勉強法 | 二次対策は『ふぞろいの合格答案』を使用して解答→採点→復習の流れで行う など |
| (一次試験) 科目別の勉強法 | 中小経営・政策は最新の中小企業白書が公表された後に勉強を開始したほうが良い など |
| (二次試験) 事例別の勉強法 | 事例Ⅳは過去問での演習よりも、〇〇の問題集を周回して基礎を先ず身に着けるほうが良い など |
| 勉強計画の立て方 | 全体の学習スケジュール、1日・1週間単位の計画 など |
| 勉強アプリやツール | 単語帳アプリ、学習管理アプリ、SNSなどの活用法 など |
自分に合った方法を取捨選択
全てを真似するのではなく、自分のスタイルや生活リズムに合わせて調整する。
その勉強方法について良いと納得ができたことを取り入れることが重要です。
まとめ ― 情報収集が合格への第一歩

中小企業診断士試験は、範囲が広く、問われる内容も知識・理解・応用力まで多岐にわたります。
だからこそ、勉強を始める前に「何を知っておくべきか」を把握しておき、合格者の行動を参考にすることが大切です。
これらの情報を集めることこそが、最初の合格戦略です。
「まずは勉強を始める」ではなく、
「正しい方向を向いてから勉強を始める」
それが、限られた時間で効率的に合格をつかむ人の共通点と言えます。
この記事が少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。
中小企業診断士の勉強を始める前に読みたい関連記事はこちら👇







コメント