こんにちは。中小企業診断士のなかりょです。
令和6年度の二次試験で、事例Ⅰ67点、事例Ⅱ70点、事例Ⅲ78点、事例Ⅳ77点の合計292点で合格しました。
「答案は予備校が出完成度じゃないといけないのでは」と思う方も多いと思います。しかし実際には、本番80分間で対応できる範囲で、戦略的に情報を整理した答案でも十分合格点を狙えます。
本記事では事例Ⅱの私の答案をもとに、設問ごとの解答意図や攻略ポイントを解説します。
この記事が少しでもお役に立てればうれしいです。
令和6年度事例Ⅱの答案例と考え方のポイント

事例Ⅱ 設問1(SWOT分析)の解答例
設問:
B社の現状について、SWOT分析をせよ。各要素について①~④の解答欄にそれぞれ40字以内で説明すること。
答案:
S:3代目のファッション業界経験と製品企画力、オンライン活用力。
W:陶磁器のデザインに新鮮味がなく安くもない、自社HPでの発信力が弱い点。
O:コロナ禍で家庭に関心を向ける若者増加、旅先での味わいを自宅で再現ニーズ増加。
T:窯元が零細で商品情報の発信力が弱い、高齢化の進行。
解答意図・攻略ポイント:
①後の設問で活用する可能性のある情報を優先する
SWOTを抽出する際は、後の設問で使う情報を優先する
記述は最後に回し、候補だけメモしておく。
事例Ⅱ 設問2(ふるさと納税の返礼品)の解答例
設問:
X市は、ふるさと納税の返礼品としてX焼を活用したいと考えている。
現在でも市の返礼品の中にX焼はあるが、全国の返礼品の中で埋もれている状態にある。3 代目は、X市から「返礼品の中でもっと目立ち、市とX焼のファンを増やすような返礼品の企画を考えてほしい」と依頼を受けた。
ブランド価値構造のうち、消費者にもたらす感覚価値と観念価値を意識して、返礼品の企画を100字以内で提案せよ。
答案:
コロナ禍以降家庭に関心を向ける若者に対して、3代目のファッション業界経験を生かして盛り付け映えや写真映えを考え抜いた返礼品を企画、X市の地場産業によるものと訴求することで、X市とX焼のファン化を図る。
解答意図・攻略ポイント:
①設問に誠実に答える
「感覚価値」と「観念価値」の2つに分けて明確に書く。
- 感覚価値(楽しさや心地よさ):盛り付け映えや写真映え
- 観念価値(ストーリーや歴史):X市の地場産業によるもの
②ダナドコ(誰に・何を・どのように訴求・効果)と裏付けを意識する
- 誰に:コロナ禍以降家庭に関心を向ける若者
- 何を:3代目の経験を生かした・・・返礼品 (裏付け=B社の強み)
- どのように:X市の地場産業によるものと訴求する
- 効果:X市とX焼のファン化 (設問内のワード引用)
事例Ⅱ 設問3(食器愛好家に対する新規事業)の解答例
設問:
X 焼には窯元それぞれの魅力があるため、3代目は、消費者がいろいろな窯元の陶磁器を手にとれる機会をつくりたいと思っている。
しかし、陶磁器祭りで接客をしていると、「あれもこれも欲しいが、家にはもうたくさんの食器がある。
収納スペースがないし、今あるものも捨てられない」と購入をためらう食器愛好家の声をよく耳にする。
3 代目は、自社や窯元の事業機会拡大を図る一方、こうした食器愛好家のニーズを充足する新規事業を手がけたいと考えている。
どのような事業内容にすべきか、100字以内で提案せよ。
答案:
食器の定期レンタルサービスを展開する。自社HPにて窯元の食器を掲載する。
窯元の認知度向上と、愛好家の収納スペース不足ニーズを満たすことで、自社と窯元の事業機会拡大を図る。
解答意図・攻略ポイント:
①ニーズを丁寧に整理する
設問情報からサブスクリプションやレンタル事業を候補とする
- あれもこれも欲しい → いろいろな窯元の陶磁器を手に取りたい
- 家にたくさん…/収納スペース…/捨てられない… → 購入は無理
②協業の前提を押さえる
単独では実現出来ないからこそ、実現能力を持つ相手と協業することが多い。
相手にとっても事業拡大の機会となる場合に協業が開始される。
このケースでは、零細な窯元単独では実現できないが、自社HPを持つB社と組むことで窯元は認知度向上を実現させる。
ひいてはB社の事業拡大にもつながるため協業の意味がある。
③ダナドコと裏付けを意識する
- 誰に:食器愛好家(既出のため解答からは省略)
- 何を:窯元の食器を
- どのように:自社HPにて掲載する (裏付け=B社の強み)
- 効果:窯元の認知度向上、自社と窯元の事業機会拡大(設問内のワード引用)
事例Ⅱ 設問4(ECサイトと店舗の顧客増)の解答例
設問:
ECサイトの新規顧客は増えたが、3代目は顧客の顔を直接見ながら販売できない寂しさも感じ始めた。
3 代目は、今後は、X市の地元で開く店舗とECサイトの両方を利用する顧客を増やしていきたいと考えるようになった。
B社にはどのような施策が必要か、150字以内で具体的に提案せよ。
答案:
自社店舗へ訪れ、X市の旅先で食べた郷土料理の味わいを自宅で再現したい顧客に対し、自社のカフェスペースにてB社オリジナルのX焼に郷土料理を盛り付けて提供する。
自社HPにてX焼と郷土料理をセットで販売する。
また、郷土料理とX焼を紹介する動画を掲載する。
以上により、自社店舗の利用者をECサイトの利用者として増加を図る。
解答意図・攻略ポイント:
①解答の方向性を決定する
「ECサイトの両方を利用する顧客を増やしていきたい」ことから、下記の2つの施策を考える
(1)ECサイトの顧客→リアル店舗へ誘導
(2)リアル店舗の顧客→ECサイトへ誘導
でも(1)は物理的に難しい顧客もいる。
また、改装した自社店舗や併設のカフェスペースは顧客の惹きつけに貢献にすると考えて、(2)を解答の軸に据える。
②ダナドコと裏付けを意識する
- 誰に:自社店舗へ訪れ、・・・郷土料理の味わいを自宅で再現したい顧客
- 何を(1):B社オリジナルのX焼
- どのように(1):カフェスペースにて…郷土料理を盛り付けて(裏付け=経営資源)
- 何を(2):B社オリジナルのX焼
- どのように(2):自社HPにて…郷土料理とセット販売(裏付け=経営資源)
- 効果:自社店舗の利用者をECサイトへ誘導する
事例Ⅱの全体攻略のポイント

事例Ⅱでは、マーケティング施策を考える設問が多く出題されます。
その際に必ず必要になるのが「ターゲット」です。
ターゲットを外すと施策の中身も本筋からズレる可能性が高くなります。
外さないターゲット設定で重要なのは、「なぜその人が買うのか=どんなニーズがあるのか」を起点に考えることです。
ニーズの構造を読み取る
与件文には、顧客や地域住民、観光客などの潜在的な不満や期待が必ず描かれています。
「誰が」「どんな状況で」「何に困っているのか、何を求めているのか」を丁寧に整理することで、施策の方向性が自然に見えてきます。
施策は「ニーズへの解決策」として考える
施策を立てるときは、「ターゲットAに○○を売る」ではなく、「ニーズXを満たすために○○を行う」と考えることが大切です。
たとえば、下記ように施策を「誰に」ではなく「何を解決するか」で説明できるようにすると、与件との整合性が高まります。
× 若年層向けに新商品を開発する
○ 若年層が「地元産に親しみを持てない」という課題を解決するために、HPで生産者の想いを発信する
ターゲット設定は「ニーズをくくる」ための手段
ターゲット設定はゴールではなく、ニーズを整理しやすくするための手段です。
「どのようなニーズを持つ層をまとめるか」という視点でターゲットを設定すると、施策との一貫性が生まれ、論理的な答案になります。
まとめ

事例Ⅱでは、「誰に売るか」よりも「なぜその人が買うのか」を意識することが重要です。
ニーズ起点で施策を組み立てることで、ターゲットを外すことが少なくなります。
ぜひ意識して取り組んでみてください。
この記事が少しでも読者の皆さんのお役に立てると嬉しいです。
事例Ⅰ(人事・組織)と事例Ⅲ(生産・技術)の記事はこちら👇
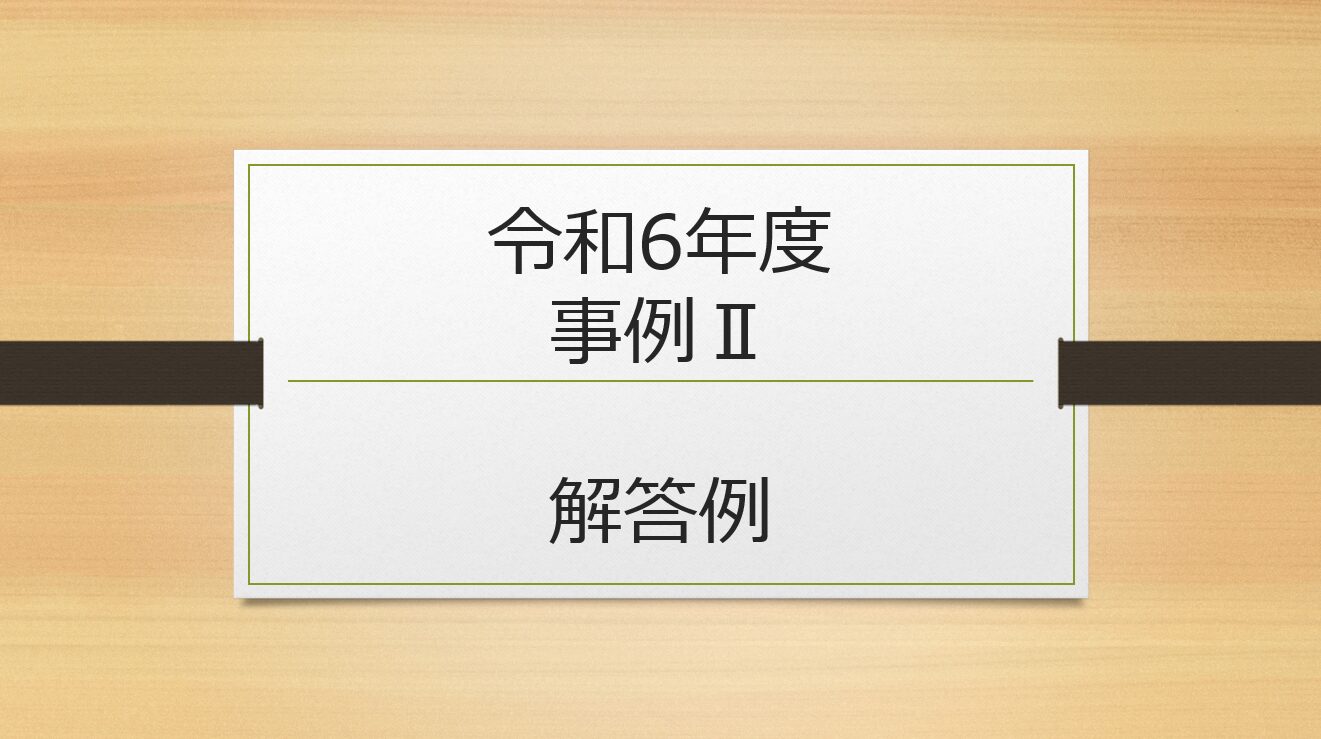





コメント