こんにちは!中小企業診断士のなかりょです。
二次試験は解答が公表されていません。
ということは、一次試験と違って「手応えがあっても落ちる」ことがあります。
私も1回目の二次試験ではそれなりに自信を持って臨みましたが、結果は不合格。
しかも、自分が最も手応えのあった事例で最も点数が低く、最も無かった事例が最も点数が高かったのです…
当時は原因がわからず、しばらく立ち直れませんでした。
それでも勉強方法と解答の作り方をコツコツと見直した結果、+67点伸ばして合格することができました。(1回目:225点 → 2回目:292点)
今回はその経験をもとに、「不合格になる人の特徴」と「そこから抜け出すための考え方」を整理してお伝えします。
この記事が少しでもお役に立てますと嬉しいです。
二次試験で不合格になる人の特徴①:設問間の位置づけを意識できていない
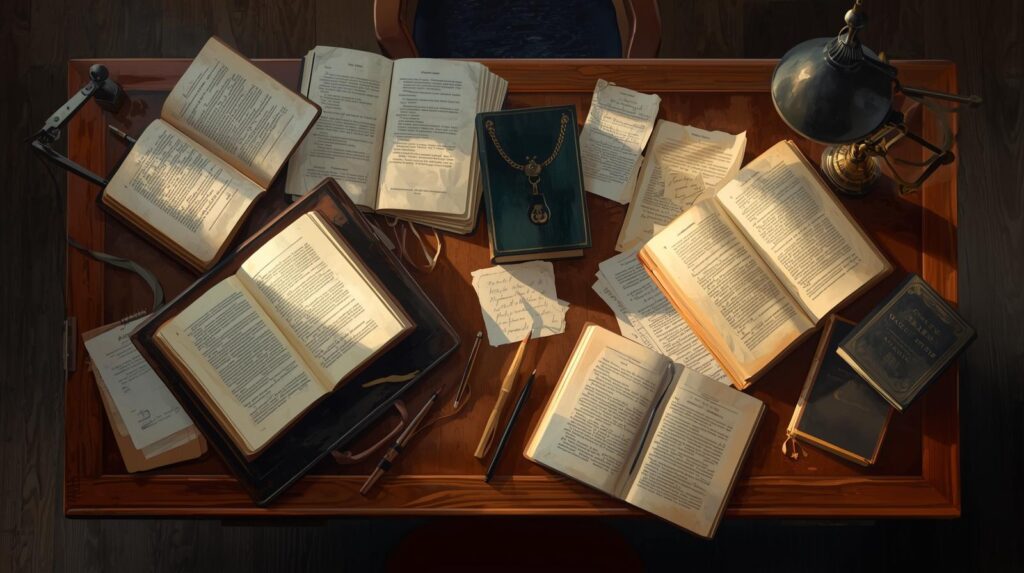
一つ目に反省したのが、「設問同士のつながりを意識できていなかった」という点です
設問1で分析したSWOTや強み・弱みを、後の設問で活かすという意識が薄かったり、
同じ要素を別の設問の解答で繰り返したり、整合性の取れない答案になっていました。
二次試験では、各設問がバラバラではなく、一つのストーリーとしてつながっています。
設問を個別に解く前に、全体を俯瞰して「どの設問が全体のどこを担うのか」を確認することが非常に重要です。
例えば令和6年度の事例Ⅰの設問を見てみます。
【設問内容】
設問1:A社の2000年当時における強みと弱み
設問2:首都圏市場の開拓のためにプロジェクトチームを組織した理由。後の2代目をプロジェクトリーダーに任命した狙い
設問3:Z社はA社に案件を持ちかけた理由
設問4(1):2024年の創業経営者の助言による配置転換の狙い
設問4(2):A社がZ社との取引関係を強化していくために必要な施策
【ストーリー上の位置づけ】
設問1:過去の成功要因と制約要因の整理(現状分析)
設問2:環境変化への対応と新戦略への転換
設問3:外部との関係性変化
設問4(1):次世代体制への移行(組織面での課題対応)
設問4(2):今後の成長に向けた戦略提言(未来志向)
全体を通してみると、
A社の現状分析を行い、現在実行されている戦略の意図を確認して、今後に向けて何に取り組んでいくべきかを考える問題であることが分かります。
これを整理しておくことで、設問全体を通して筋の通った解答が作成しやすくなります。
二次試験で不合格になる人の特徴②:解答プロセスが固まっていない

「設問解釈 → 与件文読解 → 解答下書き → 記述」
このような大枠の解答プロセスを意識している人は多いと思います。私もそうでした。
しかし、設問タイプごとに「どんな情報を探し、どう整理して書くか」というプロセスまで確立できていなかったのが、失敗でした。
この思考の流れを事前に型として定着させておかないと、80分の試験時間の緊張感では、設問ごとに考え方がブレてしまいます。
たとえば「助言問題」なら、いきなり施策を考えるのではなく、
事業環境の変化に応じたあるべき姿と現状のギャップを把握し、課題を特定してから具体策を導く、という順序でプロセスの型をつくりました。
例えば令和6年度の事例Ⅰの設問4(2)を見てみます。
設問:
今後、A社が3PL事業者となるための事業展開について、A社がZ社との取引関係を強化していくために必要な施策を、100字以内で助言せよ。
①事業環境の変化
→ 3PL事業者との競争激化
②あるべき姿
→ 組織一体での強みを活かした差別化、潤沢な委託先保有、社員のモラール向上
③現状
→ 別組織でそれぞれの強み保有、一部組織で委託先不足、人事制度の未整備
④課題
→ 強みの共有、委託先不足解消、人事制度の整備
⑤具体策
→ 組織間連携強化、組織間での委託先共有、成果主義制度導入
解答:
両事業部のお互いの強み活用によるシナジーを発揮して多様化や複雑化した物流業務へ対応する。成果主義制度の導入により社員の業務意欲向上、事業部間の外部委託先を共有することで人手不足問題への対応を図る。
設問ごとにやるべき作業(情報を整理する順序)を決めておいたことで、本番でも再現性高く解答を作成することが出来るようになりました。
二次試験で不合格になる人の特徴③:表面的なパターン解答に頼りすぎ

私は1回目の受験時、「こう問われたら、こう答える」というパターン化された解答を信じすぎていました。
『ふぞろいな合格答案』でよく見る定型フレーズを覚え、それを当てはめれば得点できると考えていたのです。
特にその傾向が強く出たのが、事例Ⅲ(生産・オペレーション)の工程改善を助言する問題です。 本来なら、事例企業の生産体制や現場の課題を踏まえて、「実態に沿った現実的な改善策」を提案すべき場面です。
しかし当時の私は、「作業の標準化」「教育マニュアルの整備」「ジョブローテーション化」といった、どの企業にも当てはまりそうな一般論ばかりを書いていました。
与件文に書かれたC社の特徴的な事情——たとえば、少人数体制で多品種対応しているとか、熟練者依存が強いとか——を深く読み取らず、単に「勉強で見たことのあるフレーズ」を並べる傾向にありました。
合格への転換点:構造 × プロセス × 現場理解
2回目の受験で合格できたのは、
次の3つを意識して勉強したことが大きかったと思います。
- 構造を意識する(設問間の位置づけを理解する)
- プロセスを固める(設問タイプ別の思考手順を確立する)
- 現場を読み込む(与件文から企業の実態を掴む)
これら3点を意識したことで、答案全体の一貫性と説得力が格段に高まりました。
まとめ

中小企業診断士の二次試験は、「知識量の勝負」ではありません。
ストーリーを読み解き、設問の意図を汲み取り、与件文から根拠を導く力が問われます。
「一つ一つの解答を作りにいく」のではなく、「企業のありのままを診断して、寄り添うように助言する」姿勢が大切なのかもしれません。
同じように悩んでいる方に、この記事が少しでも参考になれば幸いです。
関連記事はこちら👇
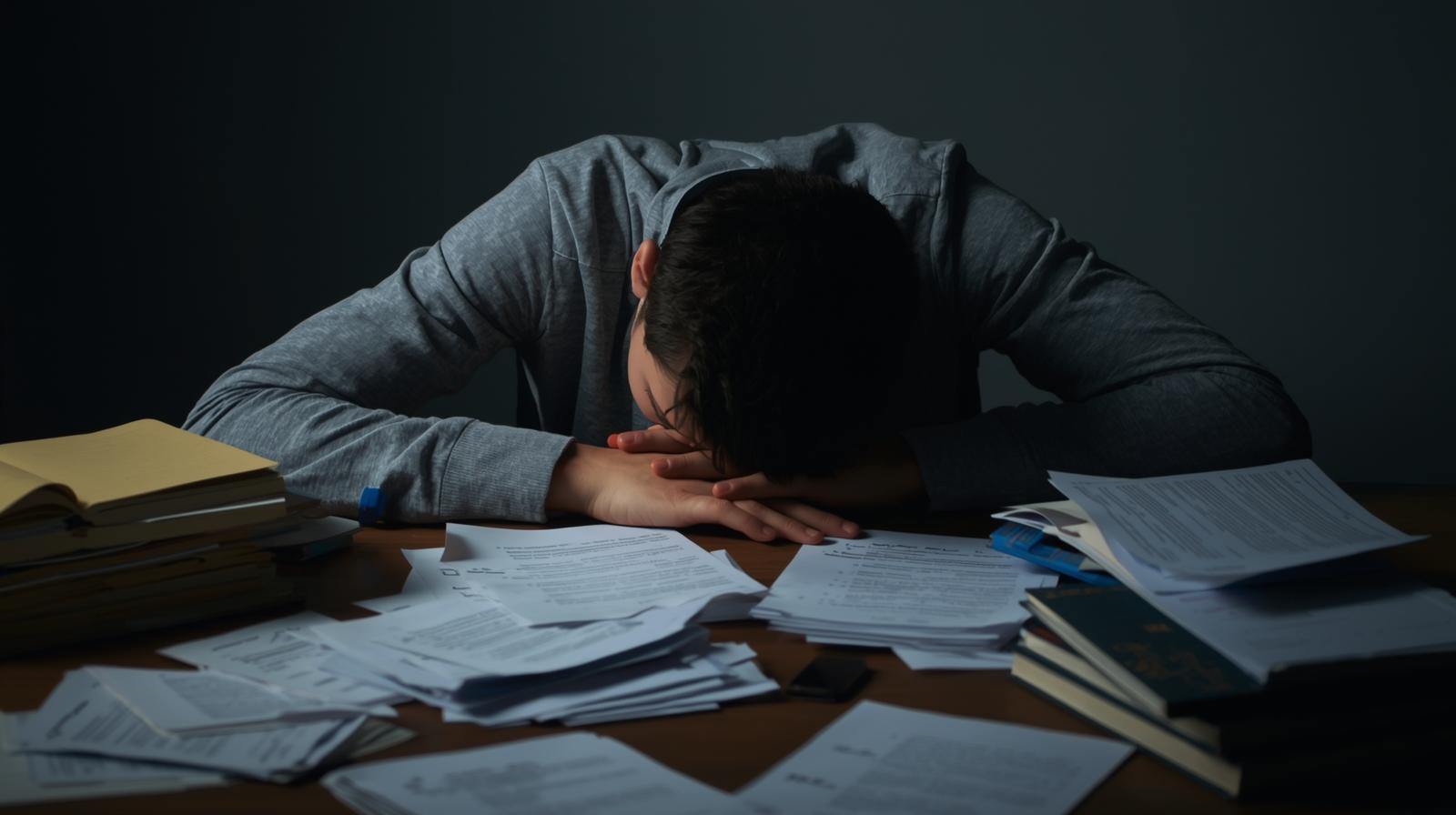






コメント