中小企業診断士のなかりょです。
本記事では、筆者が中小企業診断士試験に挑戦し、合格までの体験をまとめています。
1次試験・2次試験それぞれで取り組んだ勉強方法や、試験本番で感じたこと、そして不合格から学んだことまで、リアルに書き残しました。
わたしは1次試験を1回で通過し、2次試験は2度目の挑戦で合格。
決して要領の良いタイプではなく、社会人として働きながら合計1000時間を積み重ねてようやく合格に辿り着きました。
これから診断士試験の勉強を始めようと思っている方、あるいは勉強中で壁にぶつかっている方にとって、少しでも参考になれば幸いです。
中小企業診断士との出会い|資格の存在を知ったきっかけ

「中小企業診断士って知ってる?1年前に取ったばかりなんだけど、めっちゃおすすめだよ。資格取ってから自分の見えている世界が広がった。」
これは私がまだ20代の頃、仕事終わりの居酒屋で前職の上司(50代)が言った言葉です。
(自分の見える世界が広がるってどういう意味?)と思いながらも、
「そうなんですね、そんな資格があるんですね!」と誰でも出来るような相づちを打ってしまい、他愛もない会話で終わってしまいました。
最初に診断士の存在を知ったのは、この上司が資格を持っていたことがきっかけでした。
なぜ診断士を目指したのか|キャリアの不安と自己研鑽

診断士の存在を知った数年後…
上司が会社を辞めて中小企業診断士として独立することになったのです。
その時から資格への興味がふつふつと沸き始めます。
「どんな資格なんだろう?」、「自分の見えている世界が広がるって言ってたけど、どういう意味だったのか?」と。
資格について調べていると、「ふむふむ、経営全般の知識が見につく面白そうな資格だな」、「コンサルとして独立もできるのか、面白そうだな」と思い始めました。
また、その頃は「この会社に勤め続けることで自分のキャリアはどうなるんだろう」と漠然と不安を抱えていた時期でもありました。
将来の可能性は広げておきたいと思い、勉強を始める決意をしました。
目標の設定
中小企業診断士の資格試験は大きく分けて1次試験と2次試験を突破することで合格になります。
私は勉強を開始したのが2022年7月だったため、翌年の1次試験(8月)と2次筆記試験(10月)をストレートで突破することを目標に掲げました。
詳しくは後述しますが、1次試験は7科目の合計、2次試験は4つの事例の合計点が6割以上で合格となります。
1次試験の勉強法
受験費用をあまり掛けたくないという気持ちが強く、独学での学習を選択しました。
独学のメリットとしては、費用を抑えられることはもちろん、自分のペースで勉強できる点です。
一方で、デメリットとしては、「間違った勉強方法をしてしまうリスクがある」、「モチベーションの維持が難しい」ことが挙げられます。
これを回避するために、Youtube、個人ブログで合格者の体験談を確認したり、勉強方法について情報収集を念入りに行いました。
また、SNSで勉強仲間を見つけて、「あの人も頑張っているし、自分も頑張ろう」と思いながらなんとかモチベーションを維持していました。
1次試験に使用した教材はTACの市販テキストと5年分の過去問集です。
得意科目は本業と関連が大きい財務会計で、苦手科目は企業法務と経営情報システムでした。
暗記系の科目は直ぐに忘れてしまうため苦手でしたが、勉強期間の後半に集中的に詰め込みました。
1次試験の勉強時間|働きながらのスケジュール管理

毎日1時間早く会社へ行って共有スペースで勉強。
通勤電車の中では教科書の読み込みと単語帳アプリを使って暗記。
帰宅後の家では過去問演習やその日の復習。
というルーティンを試験日まで約1年間続けました(毎日出来ていたわけではないですが…)。
Studyplusというアプリで記録していた学習時間によると、1次試験の勉強だけで概ね500時間を費やしていました。
時間の配分は次の通りです。財務会計は本業との関連があったので若干少なめでした。
企業経営理論:90時間
経済学・経済政策:70時間
運営管理80時間
財務・会計:50時間
経営法務:80時間
経営情報システム:70時間
中小企業経営・中小企業政策:30時間
私がどうやって勉強を継続していたかは、下記記事にてまとめています。
1次試験当日の様子|本番で意識したこと
2日連続で3~4科目を受験するので集中力をキープすることがとても難しかったです。
あまり普段飲むことのないエナジードリンクを飲んで、なんとか完走しました。
出来るだけ脳を疲れさせずフレッシュな状態を保つために、当日の試験前や休憩時間は教材を開いて勉強することはほとんどせず、休憩時間も試験会場の外に出てリフレッシュすることを意識しました。
試験問題では特に経営情報システムと財務・会計が難しく、消去法でも選択肢を絞り切れない問題もたくさんありましたが、諦めずに最後まで考え抜きました。
1次試験の結果

自己採点の結果、7科目全てで合格点を獲得することが出来ました。合計476点でした。
高得点の科目は無かったですが、苦手科目についてもしっかり時間を設けて、穴を作らないように勉強したため、全科目で合格することが出来ました。
企業経営理論:68点
経済学・経済政策:72点
運営管理68点
財務・会計:64点
経営法務:72点
経営情報システム:64点
中小企業経営・中小企業政策:68点
2次試験(筆記)1回目の勉強法
1次試験と同様に独学を選択しました。
1次試験が終わるまで2次試験の勉強はほぼしておらず、先ずは1週間程度かけてYoutubeやブログ記事で二次試験の概要や勉強方法を調べました。
勉強方法としては、
独学者のバイブル的な存在である『ふぞろいな合格答案』を使って、過去問演習→採点→復習を平成28年度~令和4年度まで繰り返し行い、試験日までに合計80事例程度を解きました。
2次試験(筆記)1回目の勉強時間
1次と2次のストレート合格を目指していましたが、とにかく時間が足りません。
2次試験までの期間は1次の時よりも多めに勉強時間を確保して、合計250時間を勉強に掛けて試験本番を迎えました。
2次試験(筆記)1回目の結果
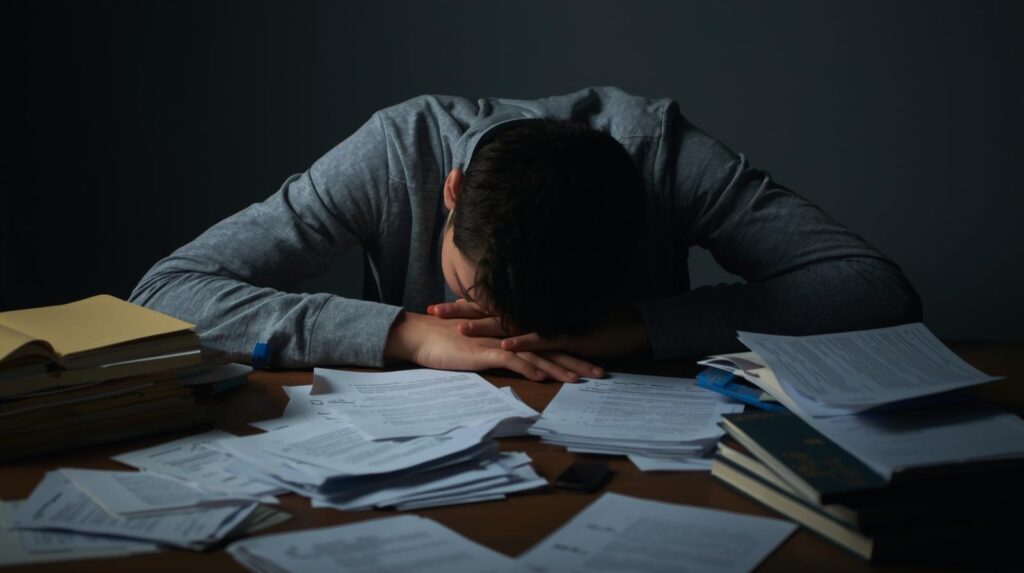
結果は225点で6割(240点)に届かず不合格でした…。
得意の事例Ⅳ(財務・会計)で得点を伸ばすことができず、事例Ⅰ~Ⅲも合格点には届きませんでした。
【点数の内訳】
・事例Ⅰ:57点
・事例Ⅱ:51点
・事例Ⅲ:57点
・事例Ⅳ:60点
事例Ⅳの試験時間が終わった瞬間、「得点を稼ぐ予定の事例Ⅳでやらかした、これは落ちたな…」と思い、2回目の受験を覚悟しました。
家までの帰り道も放心状態で、帰り道の記憶がありません。(笑)
完全なる力不足でした。
なぜ2次試験に落ちたのか(自己分析)
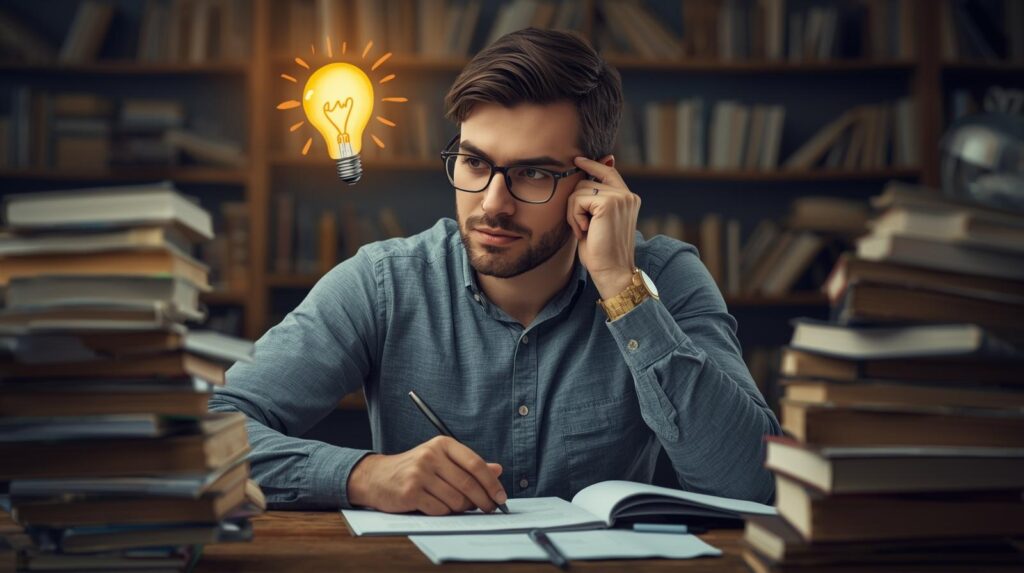
表面的なパターン解答に頼りすぎた
「こう問われたら、こう答える」というパターンやフレームワークに頼りすぎてしまいました。
事例Ⅲの工程改善を助言する問題の場合、本来は企業の状況に合わせて「実態に沿った」、「より現実的な」提案をすべきです。
当時の私は「型に当てはめれば得点できる」と短絡的に考え、「作業の標準化、教育マニュアルの作成、ジョブローテンション化」等の一般的な知識で解答を作成する傾向にありました。
要するに、事例企業の置かれた状況をを深く読み込まずに解答を作っていました。
結果的に答案は“形式的には整っている”ものの、中身の薄い解答に。
自分としては「勉強通りに書けた」と思っていたのに、点数に結びつかなかったのだと思います。
解答プロセスが確立されていなかった
1事例80分で解き切るには、練習の時と同じ力をいかに出せるかが重要になります。
解答プロセスの型が確立されていれば、それだけ有利になると言えます。
助言問題では、「内外環境の変化→企業の現状 → あるべき姿 → 課題→具体策」というような流れで情報を押さえる必要があります。
当時の自分は行き当たりばったりの解答をする傾向にあり、再現性のある解答プロセスが確立されていませんでした。
その結果、解答内容にバラツキが生じて得点が安定しなかったのだと思います。
2次試験(筆記)リベンジへ|勉強法をどう変えたか
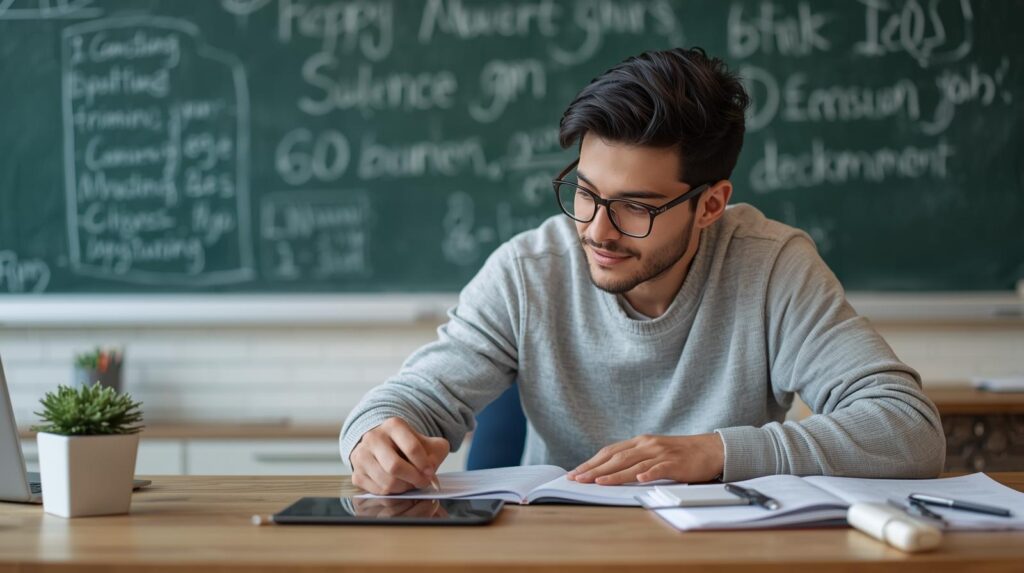
1次試験に合格すると、2回分の2次試験の受験資格が与えられます。
一度落ちてしまったので、もう一度失敗すると1次試験からやり直すことになります。
「これだけは絶対に避けたい…」と思い、予備校の利用を決意しました。
選んだのは某有名予備校の通信講座でした。
1次試験からこの予備校の教材にお世話になっていました。
また、知名度があるので受講者が多く、演習のたびに得点の順位を開示してくれるため、自分の位置を確認するのも良い刺激になると思ったことも決めてでした。
予備校にお世話になったことで良かったことは、事例を解く上での思考プロセスが確立されたこと、事例企業が抱える問題の本質を捉えた解答が作成できるようになったことでした。
また、毎回違う事例を解くので、試験本番を想定した初見問題への対応力を身に着けることが出来た点も良かったです。
2次試験(筆記)リベンジの勉強時間
2回目の2次試験のための勉強時間は約250時間でした。1次試験と1回目の2次試験を加えると、結果的に約1000時間掛かりました。
2次試験(筆記)リベンジ本番
2次試験前夜は、もう後が無い不安からあまり眠れず…
「でも、やれることはやった!」と自分に言い聞かせて試験会場へ向かい、アドレナリンが出ていたせいか眠気は特に感じませんでした。
受験会場が大学のキャンパスだったので、休憩時間はキャンパスの芝生に座ってリフレッシュを挟み、1日やり遂げることが出来ました。
合格発表の瞬間

結果は292点で合格!!
しかも1回目の受験から+67点も点数を伸ばしての合格でした。
今までの苦労が全て報われた気持ちがしましたし、何より「ホッ」としました。
【点数の内訳】
・事例Ⅰ:67点 (前回から+10点)
・事例Ⅱ:70点 (前回から+19点)
・事例Ⅲ:78点 (前回から+21点)
・事例Ⅳ:77点 (前回から+17点)
2次試験口述試験の対策
口述試験は遅刻せずに会場に行き、何かを喋れば99%合格する試験と言われています。
「でも、万が一1%に入ってしまえばこれまでの苦労が水の泡になる…」と思い、対策をしっかり行いました。
具体的には、2次試験の問題文を読み込んで想定問答を準備しました。
想定問答はいろいろな予備校がホームページに掲載しているのを参考にしました。
入念に準備をしていったものの、当日は変化球の質問は全く出ず、すんなりと終わりました。
合格までを振り返って|成功要因と失敗から学んだこと
勉強を始めた頃は1000時間も勉強が必要と知って、本当に継続できるのか不安でした。
実際に取り組んでみると、1次試験は科目のジャンルが色々で、意外と飽きずに進めることができました。
一方で大きな壁となったのが2次試験でした。
初回の挑戦で不合格になったときは、「これ以上、どうすれば得点を伸ばせるのか分からん…」と、ショックが大きくて次に向けて仕切り直すのが大変でした。
再挑戦を決意するだけでも大きなエネルギーが必要でした。

その中で特に大切だと思ったのは「自分ひとりで戦わないこと」でした。
SNSで他の受験生の状況を知ることで、自分の状況を客観的に見直すきっかけになりました。
また、予備校で添削を受けることで、解答の改善サイクルを短期間で回せるようになり、得点力を伸ばすことができました。
これから中小企業診断士を目指す方へ

診断士試験は1000時間を超える長期戦と言われます。
最初は気が遠く感じるかもしれませんが、日々の積み重ねが必ず力になります。
私自身も、最初は「本当にできるのか?」と不安でしたが、続けているうちに勉強も楽しくなり、なんとか完走することが出来ました。
また、「診断士を取ると世界が変わる」と言っていた上司の言葉は、本当でした。
会社全体のことを理解できるようになるだけでなく、人脈が一気に広がり、今まで触れることのなかった分野や価値観に出会えるようになります。
学んだ知識が自分の仕事の見え方を変え、さらに人とのつながりが新しい挑戦のきっかけになっています。
積み重ねた努力は、必ず自分の力となり未来を切り開きます。
診断士試験に挑戦される方々にとって本記事が少しでも参考になれば幸いです。







コメント